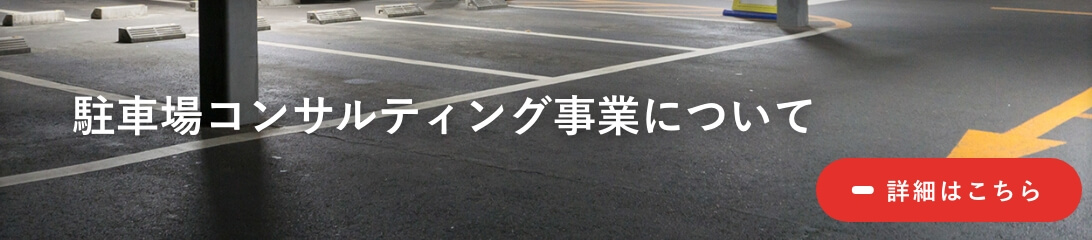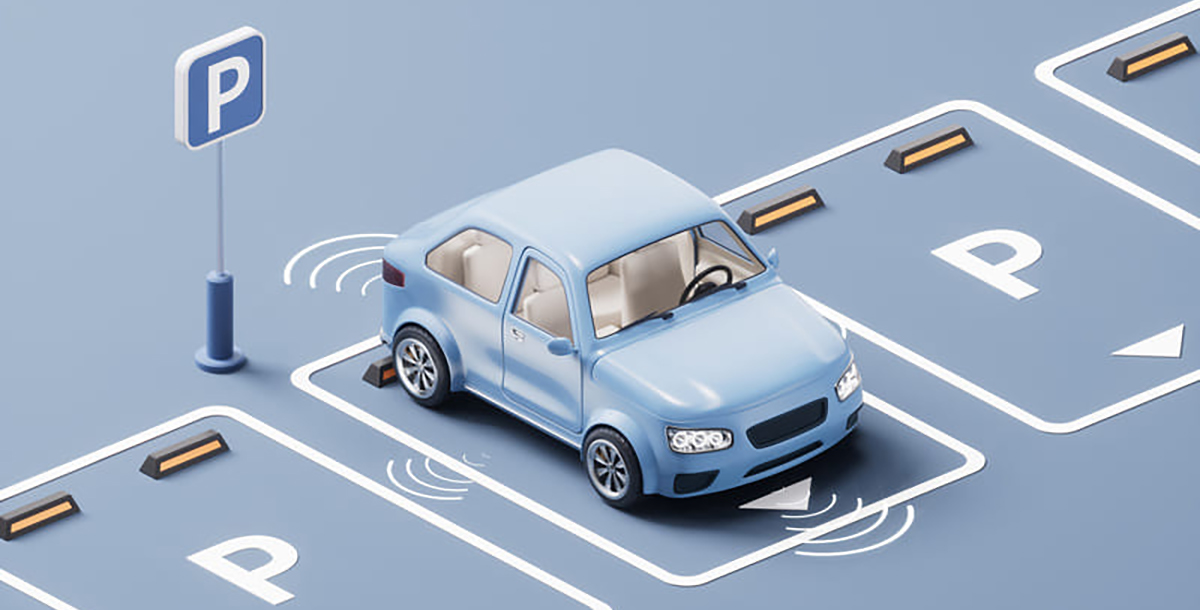ちょっとミライの駐車場③
駐車場利用者層の変化について
日本では、急速に少子高齢化が進んでいる上に、若者の車離れも進んでいるといわれており、社会の変化に伴い駐車場を利用する層にも変化が現れています。
今後、駐車場利用者層の変化に合わせ、駐車場も何らかの対策が必要になるのでしょうか。
今回は、ちょっとミライの駐車場シリーズの3回目として、駐車場利用者層の変化についてご紹介します。
INDEX
駐車場の利用者層の変化と将来の予測
警視庁の資料によると、令和4年の運転免許試験の受験者数は、前年に比べ全体で約9万人減少しており、運転免許の保有者数も減少傾向にあります。また、令和4年末時点での年齢別の運転免許保有者数を見ると、65歳以上の高齢者が約18万人となっています。
ドライバーの傾向は、駐車場利用者層の傾向に比例すると考えられます。したがって、駐車場利用者層の年齢は徐々に上昇し、将来的には車を利用する人自体の数が減るため、駐車場利用者も減少していくのではと予測されています。
また、車を個人が所有するのではなく、必要なときだけ車を利用するカーシェアリングサービスの活用も増加しています。経済産業省のデータによると、2015年から2022年の間にカーシェアリング用の車両台数は約3倍、車両ステーション数は約2倍と、右肩上がりに増加していることが分かります。このことから、今後は日常的に運転をしない、運転に不慣れな人が駐車場を利用するケースも増加するのではと推測されます。
参考:
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r05kou_haku/zenbun/genkyo/h1/h1b1s2_3.html
https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20230224hitokoto.html
駐車場を利用する車の変化
販売されている自動車を見ると、車幅が広く、車高が高い車が多くなっています。多くの車でモデルチェンジのたびに全長や幅、高さが大きくなる傾向にあるのです。
車のサイズが大きくなった背景にはさまざまな理由が考えられますが、広々とした車室空間の実現や安全性の向上もボディサイズの拡大に関係しているといわれています。また、車両重量にも変化が見られ、大型のバッテリーを搭載している電気自動車は、従来のガソリン車に比べ、重量が重くなっています。
したがって、駐車場を利用する車も大型化し、電気自動車の普及に伴い、重量の重い車両の利用が増加する傾向にあるのです。
ミライの駐車場に向けて実施すべき対策とは

駐車場を利用する人と車の変化に合わせ、駐車場自体も何らかの対応が求められる可能性があります。少子高齢化や若者の車離れによってドライバーの年齢が高くなり、カーシェアリングの普及に伴い運転に不慣れな利用者の増加が増えれば、駐車しにくい、狭い駐車場は敬遠される恐れがあるでしょう。さらに、駐車時の事故のリスクも高まると考えられます。
そのため、今後、駐車場を開発・リニューアルする際には、利用者の安全性や利便性に配慮し、車室幅を拡げる対策が求められます。
また、駐車場内での自損事故のほとんどを占めるゲート・発券機/精算機付近での事故対策として、ゲート付近に直線で乗り入れができるレイアウトや、急な発進などによるバーの損壊を防ぐ折れにくい素材のバーなどの対応も必要になるでしょう。
車の利用者が減少すれば、当然、駐車場の利用者数も減少します。その中で利用者を確保していくためには、より安全で利用しやすい駐車場の整備が求められるでしょう。
これからの未来に向けて駐車場の開発やリニューアルを検討される際には、ぜひ三菱地所パークスまでご相談ください。